我が家の娘は7ヶ月のとき、ミルクを飲むと噴水のように全部吐いてしまい、その後ぐったりと眠ってしまうという症状がありました。病院で診てもらったところ「乳アレルギー」と診断され、以降は医師の指示のもと、段階的に負荷試験を進めていくことになりました。
今回は、かかりつけのクリニックで負荷試験を受けた時の流れや、持ち物などを共有します。同じような状況の方の参考になれば嬉しいです。
負荷試験の概要と当日の流れ
今回は、かかりつけの小児科クリニックでの実施でした。クリニックには専門の設備がないため、重い症状が出た場合は大きな病院に搬送されるという説明が事前にありました。
当日の流れ:
- 朝食は軽めか、食べずに受診。
- クリニックで指定量のミルク(または牛乳)を摂取。
- 娘の場合は、離乳食に混ぜて食べました(例:おかゆ、とうもろこし、さつまいもなど)。
- クリニックの待合室で2時間待機。
- 専用の別室などはなく、一般の待合室で様子を見ます。
- 医師が30分ごとに診察してアレルギー症状の有無を確認。
- 2時間後に、結果(陰性・陽性・判定保留)を医師から説明されます。
- 結果に応じて、今後の自宅での摂取量や注意点などの指導を受けます。
当日の持ち物リスト
以下が、当日持って行ったものです。参考までにまとめます:
- 指定された量のミルクまたは牛乳(1歳を過ぎてからは牛乳OKになりました)
- ミルクに混ぜる用の離乳食(おかゆ、娘の好きなとうもろこしやさつまいも)
- 離乳食完了してからはジュース(牛乳とジュースを混ぜて)
- 朝ご飯(負荷試験前は軽め or なしのため、試験後に食べさせる用)
- お茶
- 処方されているアレルギーの薬
- オムツ
- おもちゃ(待機時間に退屈しないように)
自宅での乳摂取に関する注意点
負荷試験で「陰性」だった場合、その時に摂取した量を自宅でも定期的に摂取するよう指導があります。医師からは以下のような注意点がありました。
- 摂取は病院が開いている時間帯に行う
- 体調が良いときに行う
- 摂取後1時間は運動・入浴を避ける
- 症状が出た場合はすぐ病院に相談・受診する
- どんな症状の時に、どれくらいの時間内に病院を受診すべきかの「プリント」をもらい、事前に説明もありました。
負荷試験で「保留」だった場合、今までの量をどれぐらい続けるか説明がありました。
幸いなことに娘は「陽性」になることはありませんでした。
定期的に血液検査もして、娘の症状や年齢をみながら進めてくれたので陽性にならなかったのかな?と思います。
次のステップについて
医師からは、例えば「週〇回この量を食べさせて、〇回クリアしたら次の負荷試験を予約してください」など、具体的な進め方を教えてもらいました。
また、同じ量の乳製品を含む加工品(ビスケット、食パン、バターなど)では、どの商品が今の段階で食べられるかも教えてもらえました。
信頼できる医師との出会いの大切さ
我が家のかかりつけの先生は、とても丁寧に説明してくれる方で、
- 今後の進め方
- 症状が出たときの対応
- 質問への対応
など、こちらの不安や疑問にも丁寧に向き合ってくださいました。
アレルギー対応は長期戦になることもあるので、信頼できる先生を見つけることがとても大切だと感じています。もし今のかかりつけに不安がある場合は、他の小児科を受診することも一つの選択肢だと思います。
同じような状況のお子さんを持つ保護者の方の参考になれば幸いです。
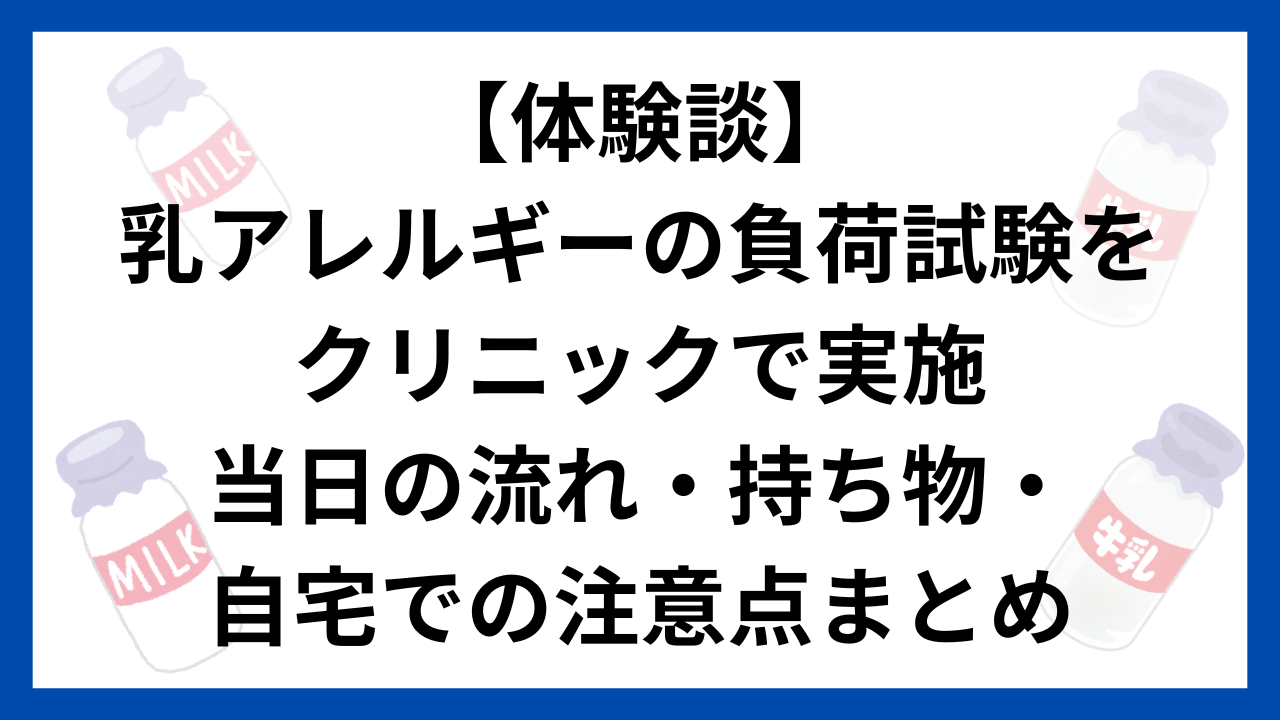
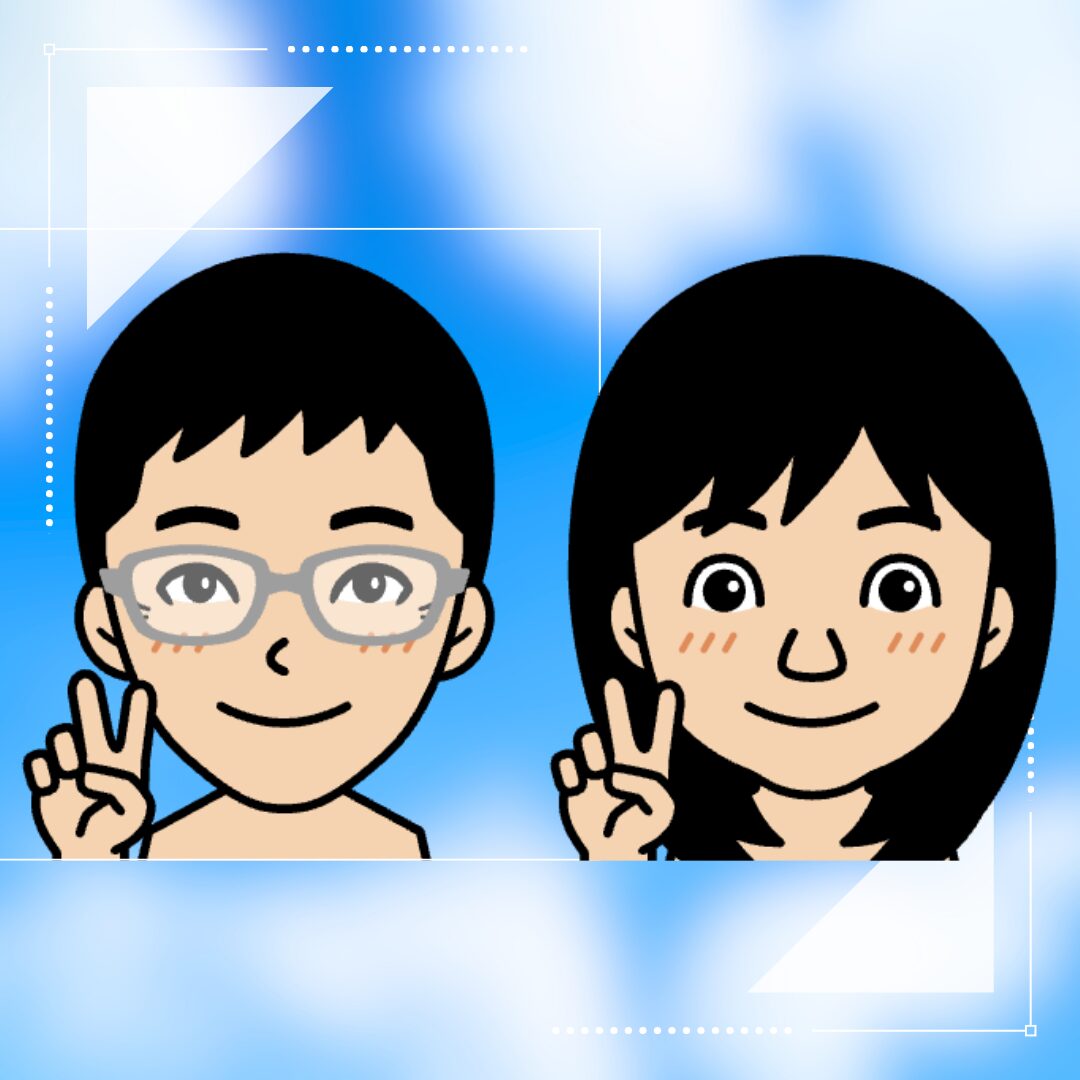
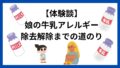

コメント